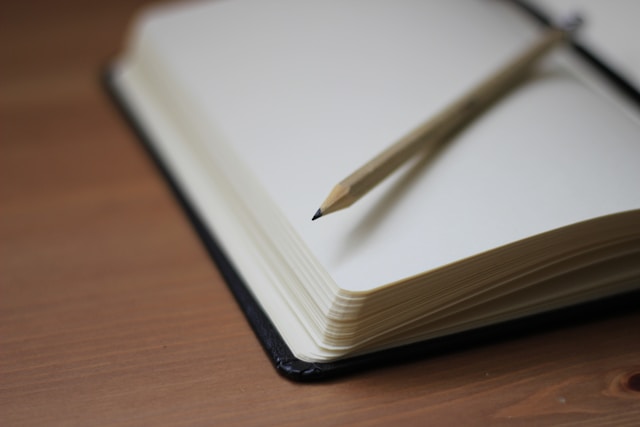生井利幸先生から、日々、多くの耳学問(注)を教授いただきます。それらは、一般的な学校では学べないこと、教科書にも記されていないことです。本ページでは、それらの学びの一端を「今日の学び」として、少しずつご紹介して参ります。
(注)「耳学問」とは、大教室でテキスト通りの方法で学ぶ方法ではなく、学習者が直接、教授者から、「難しい学問について、学習者にとって最も妥当な方法で学ぶ方法」を指します。
もののあわれ
「もののあわれ」とは、平安時代から続く日本の精神文化の一つであり、国文学者・本居宣長によって広く知られるようになった概念です。日本人なら誰もが耳にしたことがあるでしょう。しかし、それが何であるのかを明確に説明できる人は多くはありません。
もののあわれを理解するために、まず、感じるという心の動きについて考察します。人間は、日々、様々なことを感じながら生きていますが、その感じ方には大きく二つの種類があります。
一つは、能動的に感じるもので、自分の内側から湧き上がってくる感情です。喜びや悲しみ、嬉しさや苦しさ、といった、個人的な感情がこれに当たります。
もう一つは、自然や人々の様相など、自分以外の外界の事物によって揺さぶられて感じるものです。桜のはかなさに美を感じたり、枯れ葉や倒木に寂びを覚えたり、雲海に神秘を見いだしたりする感情が該当します。これらは個人的な感情ではなく、他の人にも起こり得る感情であり、一般的な日本人であれば自然に抱くものです。
この外界に触れて生まれる感情こそが「もののあわれ」です。そして、日本特有の文化とされる「もののあわれ」ですが、実のところ、国籍や文明・文化に関わらず、人間に本来的に備わっている能力、感性がそこにあるのです。
また、もののあわれは無常観の一つでもあり、「今が最も美しい」という考えが内在しています。春、桜の花びらが風に舞い、桜吹雪となる瞬間。そこには一瞬の命の輝きと、永遠には続かないからこそ生まれる美しさがあります。永続しないものだからこそ、その一瞬が尊いと感じられるのです。
人間の命もまた、桜と同じく、つかの間のものです。そして、川の水に二度と同じ水が流れることがないように、人生もまた、二度と同じ時間を経験することはできません。だからこそ、今という瞬間を美しく輝かせ続けたいものです。
「もののあわれ」に関する生井利幸先生の動画講義
外見は内面の鏡である
「人を外見で判断してはいけません」。多くの人が幼い頃に教わる言葉です。確かに、生まれつきの目鼻立ちや肌の色といった容姿は選べません。しかし、歳月を重ねるうちに、外見にはその人の生き方が刻まれていきます。つまり、内面が形となって顔に表れるのです。
この考えを裏付ける興味深い例として、長年チンパンジーの研究に携わってきた学者の話があります。彼女の顔が、どこかチンパンジーに似ているというのです。「似ていますね」と伝えると、彼女は嬉しそうに笑いました。日々向き合い、愛情を注ぎ、深い関心を寄せてきた対象が、無意識のうちに表情や雰囲気に影響を与えるのでしょう。
アメリカ第16代大統領リンカーンは、「四十歳を過ぎたら、自分の顔に責任を持て」と言ったとされます。これは、外見が単なる生まれつきのものではなく、その人の性格や心の在り方が表情や雰囲気に反映されるという考え方です。実際、多くの人を見てきた指導者や経営者も、同様の見解をしばしば口にします。
いつも不平不満ばかり口にする人は不満げな顔つきに、欲深い人はどこか欲深い表情に、意地悪な心を持つ人は意地悪な雰囲気に変わっていきます。一方で、他者への思いやりに満ちた人は柔らかな表情に、慈悲深い人は穏やかな顔に、凛として生きる人は凛とした佇まいになります。日々の心の持ち方が、その人の外見を形づくるのです。
顔は嘘をつきません。心の在り方、日々の生活、人生経験を通して感じ、考えてきたことなど、すべてが外見として表れます。外見とは、内面が長い時間をかけて形づくってきた、その人の「真実」なのです。
したがって、外見を磨きたいのであれば、まず内面を整え、心を豊かにすることが大切です。格好よく生きれば格好よくなり、清く正しく生きれば美しくなる。結局のところ、外見は自らの生き方が作るものです。すべては、自分自身の心の在り方次第です。
プロフェッショナルな人ほど基礎を大切にする
多くの英語学習者には、中学校で学ぶ基礎英語には関心を示さず、難しい単語や高度な表現ばかりを覚えようとする傾向があります。しかし、語学に限らず、どのような分野においても基礎こそが最も大切であり、日々継続して取り組むべきものです。なぜなら、基礎はすべての土台となるからです。基礎が不十分なまま難しい内容に取り組んでも、身に付くことはありません。たとえ一時的に理解したように感じても、後に総崩れしてしまいます。ましてや暗記だけで覚えた場合は、いずれすべてを忘れてしまいます。
このことは、さまざまな分野のプロの日々の過ごし方を見れば明らかです。例えば、プロの翻訳家は専門用語を扱う機会が多いものの、最も重視しているのは基礎的な語彙や文法です。彼らは毎日欠かさず基礎の勉強を続けています。スポーツの世界も同様です。プロ野球選手であっても、毎日バットの素振りや守備練習といった基礎練習を繰り返します。これは、小学生のリトルリーグから中学、高校、そしてプロに至るまで変わりません。音楽の世界でも、世界的なオペラ歌手が難曲ばかりを歌っているわけではなく、日々の発声練習という基礎を積み重ねています。
以上のように、基礎とは簡単なものではなく、むしろ最も重要なものであり、本質そのものなのです。そして、このことは語学、スポーツ、音楽をはじめ、あらゆる分野に共通して当てはまります。
清貧という生き方
清貧とは、余計なものを持たず、清らかに生きることを意味します。
21世紀の今、私たちは、多くの物と情報に囲まれ、何一つ不自由のない快適な生活を送ることができます。暑いときにはエアコンをつけ、雨で洗濯物を干せないときは乾燥機を使い、知らない街を歩くときには地図ではなくスマートフォンを頼りにする。このような便利さに囲まれた生活は一見すると豊かに感じます。しかし、あり過ぎる物や利便性は、かえって人間を盲目にします。本当に大切なものを見えなくし、心を貧しくします。
また、人間の所有欲というものは、物を持てば持つほど強まります。例えば家を手に入れたら次はもっと広い家に住みたいと考えます。生活に十分な収入があっても、さらにお金を求め、旅行に行きたいなどと考えます。情報を得ると、さらに次の情報を追い求めます。欲は底なしです。
一方で、現代社会にあっても、世俗から隔絶された生活を送っている人々がいます。フランス・アルプスの山麓に佇む小さな修道院には、余計なものは何一つありません。修道士の部屋には聖書と、小さな机と椅子といった簡素な家具だけ。時計すらなく、鐘の音が必要な時を知らせてくれます。物質的なものは必要最小限のものしかなく、あるのは、澄んだ空気と静寂、そして穏やかで満ち足りた心です。
もちろん、現代に生きる私たち全員が修道士のように暮らすことはできませんし、物を持つことが悪いわけでもありません。ただ、ほんの少しだけ自分の持ち物を見直し、「今のままで十分」と思うことができたら、これまで気づかなかった大切なものが見えてくるのではないでしょうか。
過剰な所有や行き過ぎた利便性は、本来の人間として大切なものから私たちを遠ざけ、清貧という生き方は、生の質を磨いてくれます。
アレキサンダー大王の戦術から学ぶ、「おとり」の概念
アレキサンダー大王は、マケドニア(現在のギリシア北部の山岳地帯)の王子として生まれ、やがてペルシアを自らの領土に収めたいと考えるようになり、戦争を始めました。しかし、ペルシア軍はマケドニア軍とは比べものにならないほどの大軍で、正面からぶつかれば勝ち目はありません。
そこでアレキサンダー大王は、巧妙な作戦を仕掛けます。まず、小隊をペルシア軍の端の方へ走らせ、敵の注意を引きつけました。ペルシア軍は小隊の動きに気を取られ、戦力をそちらへ集中させます。その隙を突き、アレキサンダー大王は自ら率いる少数精鋭の部隊でペルシア軍の後方へ回り込み、奇襲を仕掛けました。突然の攻撃に驚いたペルシア軍の指揮官は戦場から逃走し、指揮系統を失ったペルシア軍は総崩れとなって敗北します。
これは典型的な「おとり作戦」です。この「おとり」という概念は、軍事の世界だけでなく、現代のビジネス社会でもさまざまな場面で応用されています。
人は、そう簡単には変われない
毎年のように「今年こそはもっと自分に厳しくしよう」「不注意をなくそう」「もっと物事を前向きにとらえよう」と誓いを立てても、気がつけば一年後、何も変わっていない。そのような経験を持つ人は多いのではないでしょうか。誰しも自分を改善・向上したいと願い、より良い自分を目指して目標を掲げます。そして最初のうちは、目標どおりに頑張ります。ところが、多くの人が次第に元の習慣へと戻ってしまいます。長年積み重ねてきた生き方はそう簡単には変わらないものです。なぜなら、そのままでも大きな支障なく生きてこられたからです。
しかし、本気で変わりたいと願うならば、人は変わることができます。「変わらないと後がない」と自分に言い聞かせ、命で行えば変わることができます。なりたい自分になることができます。
変われるかどうかを決めるのは、環境でも他人でもありません。すべては自分次第です。
組織の中の人の心理と行動
人間である以上、誰しも多かれ少なかれ、好きな人・嫌いな人、気の合う人・合わない人がいるものです。しかし、社会の中で生きていくためには、上手に人間関係を保つ必要があります。特に会社などの組織では、人間関係が悪化すると居心地が悪くなり、仕事そのものよりも人間関係を理由に転職する人が多いのが現実です。その証拠に、転職した人の多くは、転職先でも同じような仕事を続けています。
そこで以下に、組織の中で見られる人の心理と行動について、いくつかの例を紹介します。これらを理解した上で自分を上手にマネジメントできれば、人間関係をより良く構築でき、苦手な相手との会話も楽しくなり、さらには自分自身の成長にもつながります。
①共通の敵(嫌いな人)がいる二人は仲良くなる
ある会社に、鈴木さん、田中さん、佐藤さんの3人がいるとします。鈴木さんと田中さん、鈴木さんと佐藤さんはそれぞれ面識がありますが、田中さんと佐藤さんは顔見知り程度で、ほとんど話したことがありません。また、田中さんは以前から鈴木さんを快く思っていません。ある時、鈴木さんと佐藤さんが仕事で衝突し、佐藤さんは鈴木さんに対してネガティブな感情を抱くようになります。すると、それまで接点の少なかった田中さんと佐藤さんが急に仲良くなり、ことあるごとに鈴木さんの悪口を言い合うようになります。これは、「共通の敵がいると結束が強まる」という人間の本能です。
②上司は、自分を嫌う部下を排除する傾向にある
人は、自分が好意を持っている相手から嫌われても、意外と気にならないものです。しかし、自分が嫌っている相手から嫌われると、強い不快感を覚えます。つまり、「自分より下だと思っている相手に見下されること」が許せないのです。
もし上司に2人の部下がいて、どちらかを異動させる必要がある場合、上司は「自分が嫌いな部下」よりも「自分を嫌っている部下」を優先して異動させようとします。逆に、自分が苦手な部下であっても、その部下が自分を慕ってくれるなら、嫌悪感は帳消しになります。人事評価や異動は、どれだけ基準を整えて公正性をうたっても、最終的には人が決めることです。そのため、どうしても好き嫌いが影響してしまいます。
③組織では、本心より損得勘定が優先される
これは説明の必要もないでしょう。組織の中で、自分が損をしてまで本心を貫く人はほとんどいません。多くの人は、自分を守りながら上手に立ち回っています。
これらの心理は、文明・文化を超越した共通の人間の心理です。世の中に、嫌いな人が一人もいないという人はいません。人の好き嫌いは誰にでもあります。しかし、嫌いな相手をただ避けるのか、それとも「自分を成長させてくれる存在」と捉えるのかで、その後の人間関係が大きく変わります。苦手な相手を「こんな人は珍しい」「この人がいてよかった」と思って積極的に会話してみると、いつしかそれが本当になります。会話も楽しくなり、自分の学びにもなります。嫌いという感情は、どれだけ隠しても相手に伝わるものです。しかし、それが相手に伝わっても何一つ良いことはありません。特に組織の中では、人間関係が自分に返ってくるものです。ぜひ、今日から、嫌いではなく「興味深い人」として相手と向き合ってみてください。きっと新たな発見があり、いい関係が築けるはずです。
嫌な人と率先して話をするように試みると、さらに先へ行くための道が見えてくる。(生井利幸公式サイト「今日の言葉」より)
月を見るという経験を通した思考
私たち人間は、日々、様々な事を感じ、考え続けています。しかしながら、与えられた脳を十分に使っている人間は存在しません。「私は十分に脳を使っている」と言う人がいるかもしれませんが、人間が本来使うことができる能力と、実際に使っている能力とはまったく別のものです。もし人間が脳の使い方を理解できれば、宇宙をも呑み込むことができます。本来、理性とはその脳の使い方を知るためにあるものです。しかし、脳を宇宙と同じように広大に使っている人、そこまでの使い方を知っている人は存在しません。誰においても、人間の思考は狭い範囲の中で右往左往しているのが現実です。
それでも、日々思考を重ね、思考の幅と深さを広げていくことで、私たちは“宇宙を旅する”ことが可能になります。その観点から、月を見るという経験を通した思考は初歩的な訓練になります。月は肉眼で見ることのできる天体です。月を眺め、地球と月の距離感を体感してみてください。地球と月の距離感がつかめたら、それを目安として月と太陽を対比させることで、地球と太陽との距離感も見えてきます。その先へも進むことができます。日々の思考の連続により、目に見えないところへも旅することができるのです。
また、月を見ながら、1969年に人類が初めて月面を歩いた出来事、人類が歩んできた歴史を思い返してみてください。そうすれば、自分が何者で、今どこにいて、これから何をすべきかが見えてくるはずです。ロマンティックになってください。ロマンティックな人だけが、さらにその上にある“入り口”を見つけることができます。
‟超越的”理性的存在者は、地球はもちろんのこと、太陽系、銀河系、そして、宇宙空間の隅々まで行くことができる。(生井利幸公式サイト「今日の言葉」より)
人のことを考える空間
人間、生きていれば実に様々な出来事に直面します。家族の介護が必要になったり、仕事が多忙を極めたり、突然の病気で闘病生活を余儀なくされたりすることもあるでしょう。そのようなとき、普段どれほど穏やかな人でも、自分のことで精一杯になり、他者の気持ちを受け取る余裕をなくしてしまうことがあります。
ところが、世の中には、どのような大変な状況にあっても、一個の人間としての輝きを失わずに成長し続ける人、そして常に人との関わり方が上手な人がいます。彼らに共通しているのは、心の中に「人のことを考える空間」を持っているという点です。その空間があれば、どんなに自分が辛く苦しいときでも、他人の親切心を受け止めたり、感謝したり、人の気持ちを察したりすることができます。そして、この空間の有無が、生の質を大きく左右します。
では、この「空間」はどうすればつくれるのでしょうか。哲学や倫理学を学ぶ必要はありません。むしろ、理論だけ学んでも身につきません。大切なことは、日々のコミュニケーションを振り返ることです。「あのとき気を遣ってくれたのに、うまく応えられなかった」「親切で言ってくれたのに、つい冷たい態度をしてしまった」などと、その都度、自分の言動を内省することで、人は経験的に心の中に「人のことを考える空間」をつくり、それを維持できるようになります。
また、多くの場合、年齢を重ね、自分自身が大変な思いを経験することで、人の気持ちを考えるようになり、人の痛みや物事の価値がわかるようになります。逆に、苦労をしたことのない人は、人の気持ちよりも自分の気持ちを優先しがちです。
皆さんの周りに、常に穏やかで人に優しく、周囲に気を配る人がいたら、その人は人一倍苦労してきた人かもしれません。そして、そういう人に限って、他人にそれを微塵も感じさせません。しかし、その人はとても「いい顔」をしている人だと思います。顔には、その人の生き方が表れるのです。
人は、大変なとき、自己中心的に陥りやすいものです。しかし、ここまで述べてきたことを頭の片隅に置いておくことで、困難な状況に直面したときでも、落ち着いて自分と向き合うことで、意識的にその空間をつくることができるでしょう。そうすることで、人の気持ちを忘れない人間であり続けられるのではないでしょうか。
優越感と劣等感
インターネットが普及し、SNSなどのコミュニケーション手段が急速に広まった現代では、誰もが簡単に自分の意見を発信できるようになりました。本に対する感想なども、気軽に書き込める時代です。真摯な感想や感謝の言葉は、筆者にとって励みになるだけでなく、他の読者にとっても気づきを与えてくれることがあります。
一方で、他人への嫉妬や劣等感から、自分は安全な場所に身を置いたまま、匿名で他者を貶めたり、本を批判したりする人もいます。「他人の真実は知りたいが、自分の真実は隠しておきたい」――これは人間のネガティブな側面の一つです。
しかし、劣等感を抱えたまま身を隠し、自分より優れていると思う相手を批判して優越感に浸っても、自分の成長に繋がることはありません。むしろ、人としての品位や品格を損なうだけです。
もし前向きに自分を改善したいのであれば、他人を批判するのではなく、自分が気にしていること、自分の中にある劣等感と向き合い、それを人に話すことです。自分の弱さや劣等感を言葉にして他者に伝えられるようになると、人はそこから解放されます。そして、それを笑って話せるようになれば、その日から人生は変わります。
劣等感は誰にでもあるものです。それが他人に知られそうになると、私たちはつい蓋をして隠そうとします。しかし、隠し続けていては、そのまま人生が終わってしまいます。劣等感を持つこと自体は、決して悪いことではありません。むしろ、自分に対する厳しい姿勢の表れであり、高貴なことです。逆に、優越感に浸るほど愚かなことはありません。見るところから見れば、人と人との違いなどは、大差のないこと、つまらないことです。
本来、人間を一個の個として捉えたとき、他者との比較に意味はありません。大切なのは、自分自身がどうあるかです。
文化と芸術
文化と芸術。この二つの言葉はしばしば並列して用いられ、ときに同類のものとして扱われることがあります。しかし、本来は異なる概念を指す言葉です。
文化とは、文明という大きな枠組みの中で、そこに暮らす多くの人々が長い時間をかけて育んできた、美しい心であり、社会基盤の一つです。これに対して芸術は、一個の芸術家が創り出す作品を指します。具体例を挙げるなら、茶道は一個の人間が創ったものではなく、長年育んできた日本文化の一つです。一方、茶道で用いられる茶碗は、一人の陶芸家が生み出した作品であり、芸術に属します。
私たちは日常で何気なく言葉を使っていますが、その意味を深く知らないままにしていることも少なくありません。 しかし、言葉は人類の歩みと切り離すことができない大切なものです。一語一語を丁寧に扱い、分からない言葉は辞書を引きながら、その重さ・深さを味わってみてはいかがでしょうか。時には、その言葉の奥に、人間が歩んできた歴史や人々の心を垣間見ることができるかもしれません。
不自由であることが自由
「不自由であることが自由」とは、いったいどういうことなのでしょうか。
ある女性は、自ら起こした会社の社長として成果を上げ、出資者にも恵まれ、念願のお店を開くことができました。彼女はその店で、一人ひとりのお客さんと真摯に向き合い、心身ともに健康に生きる力を届けたいと願っていました。ところが出資者は、自身が開発した商品を店に置いて販売することを条件とし、経営方針でもたびたび意見が衝突しました。そして、とうとう彼女は、店を手放す決断をします。その後、彼女は自分の会社までも後進に譲り、縁もゆかりもない土地で、地域の協力隊の一員としてゼロから猟師の道を歩み始めました。住まいは古い空き家を自ら再生した家。都会のマンションとは比べものにならない環境です。仕事も、暮らしも、収入も、これまでとは何もかもが違います。それでも、彼女の笑顔はまぶしいほどに輝いています。
また、ある男性は長く生物学の研究を続けていました。周囲の人々は、彼がそのまま大学で研究者として歩むものと思っていました。しかし彼は、一般企業への就職を選びます。企業は当然ながら営利を追求します。どれほど社会貢献を掲げていても、経営を無視して損をし続ける企業はありません。したがって、社員に利益を生まない仕事や、会社の利益追求に反する仕事をさせることはありません。それでも彼は定年までその企業で働き、後にこう言ったそうです。 「やりたいことができた」 と。大学という自由度の高い環境を離れ、企業という制約の多い場に身を置きながらも、彼は自分のやりたいことを見出し、企業にも自分の価値を提供し続けたのです。
つまり、彼女も彼も、本当の自由を手に入れたのです。 そして本当の自由とは、どのような仕事をしているか、どのような環境にいるかといった外側の条件にあるのではなく、生きる本人の心の中にあるものなのです。
経済社会の中で生きていくためには、お金が必要です。そのために働くことは悪いことではなく、むしろ必要不可欠なことです。しかし、人間は「生きるために食べる」だけの存在ではありません。何のために生きるのか。何のために働くのか。それらの問いに向き合い続け、自分が進むべき道を見出すことこそ、人が真に自由に生きるための第一歩なのだと思います。
心の中にこそ、真の意味での自由が存している。(生井利幸公式サイト「今日の言葉」より)
「殺意」について哲学する
私たちは日常的にニュースなどでさまざまな事件を見聞きします。その中には、人が人を殺すという痛ましく悲しい事件も少なくありません。では、どのような人が殺人事件を起こすのでしょう。実は、多くの場合、ごく普通の人が突発的に人を殺してしまいます。事件後、近隣住民が「いつも明るくて親切な方で、とても人を殺すような人には見えませんでしたので驚いています」と言うのを耳にしたことのある人も多いのではないでしょうか。
人が他者を殺害するとき、その心の中には「殺意」があります。そして、この殺意は大きく二つに分類できます。一つは、相手に対する強い「憎しみ」に基づくものです。大切な家族を故意に奪われたときや、深く愛した相手から裏切られたとき、人は強烈な憎悪を抱き、「自分がどうなってもいいから相手を殺したい」と思うことがあります。
もう一つは、「この人さえいなければいいのに」という感情です。例えば、長年連れ添った夫婦であっても、妻が夫に対して「この人さえいなければ、もっと自由に生きられるのに」と感じることがあります。また、職場で「この同僚さえいなければ自分が活躍できるのに」と思うこともあります。この場合、相手を憎んでいるわけではなく、自分の思い通りに生きるうえで相手が「不都合な存在」になっているのです。親が子を殺すという痛ましい事件もありますが、これも子どもへの憎悪ではなく、「自分が生きていくうえで子が負担になった」という心理が背景にあるためです。
「自分に限って人を殺すなどあり得ない」「人を殺そうと考えたことは一度もない」と思うかもしれません。しかし、「殺意」とは特別な感情ではなく、日々の人間関係の中でごく普通の人が抱き得るものです。とりわけ後者の「この人さえいなければいいのに」という思いがふと頭をよぎることは、誰にでもあることなのです。そして、その感情が自分の中で膨らみ、何かをきっかけに制御できなくなったとき、人は誤った行動に踏み出してしまうのです。
殺意を抱き他者を傷つけてしまう可能性は、誰にでもあり得ます。だからこそ、このような心の動きを認識・理解しておくことが重要です。これらを身の回りの人間関係に類推適用し、自分の感情コントロールやコミュニケーションに役立てることで、最悪の事態を未然に防ぐことができるはずです。
英知は日常生活の中にある
「英知」と聞くと、日常とは遠く離れた特別な場所に存在するもののように思われがちです。しかし、実際には英知そのものは、私たちのごく身近な日常生活の中にあります。例えば論理的思考は、日々の暮らしの中で、人にわかりやすく物事を説明したり、状況を適切に把握・判断したりする際に欠かせません。また、論理的思考は机に向かって勉強すれば身につくというものではなく、実際の日常生活における経験を通して磨かれていくものです。同様に、「勉強」と「日常生活」は本来、別々のものではなく、同じものなのです。
ところが日本では、勉強と日常生活が別物として扱われます。小学校の夏休みの計画表では、「勉強の時間」と「遊びの時間」が明確に分けられます。ここでいう「勉強の時間」の「勉強」とは、机に向かって行う典型的な学習を指しています。しかし、これは固定観念にほかなりません。
本当の学びは、日常生活そのものであり、学校での学びはその一部にしかすぎません。子供は友達と喧嘩したり仲直りしたりする中で、人間関係のあり方を少しずつ学んでいきます。また、学校や地域社会との関わりを通して、社会とは何かを徐々に理解していきます。自由に遊ぶ時間は、創造性や新しい発想を育む貴重な機会です。実際、近年では創造性を重視し、小学校入学後すぐには机に向かわせない教育方針を採用する学校もあります。
もし小学校の先生が、「日常生活そのものが学びの場である」と教えることができたなら、子供たちの勉強に対する興味や姿勢、そして将来の生き方までも、より善い方向へと向かっていくのではないでしょうか。
頻繁に遅刻する人の心理構造
しっかりしていて周囲への気遣いもできるのに、待ち合わせだけはいつも遅れてくる。仕事はできるのに、なぜか遅刻が多い。あなたの周りにも、このような人がいるかもしれません。実はこうした人は、自分では気づかないうちに「遅刻すること」が行動様式として固定化されている可能性があります。
人間は、自分の行動様式の中に“道筋”をつくります。 例えば、どれほどお腹が空いていても必ずお風呂に入ってから夕食を食べる人、逆に、お風呂の前に必ず夕食を済ませる人。毎朝会社に行く前に、必ずカフェに立ち寄って熱いコーヒーを飲む人。これらは単なる習慣ではなく、その人が無意識のうちに「そうする道筋」をつくっているからです。わかりやすく言えば、その人の“癖”のようなものです。
さらに言うと、会社に行く前に必ず熱いコーヒーを飲む人は、そうすることによって無意識のうちに心と身体を仕事モードに切り替えています。逆に、電車の遅延などでコーヒーを飲めない日には、どこか調子が出ないと感じるでしょう。朝起きて窓を開け、新鮮な空気を吸い、朝日を浴びることで「今日も頑張ろう」と心身が整うのも、無意識のうちにつくられた道筋の一つです。このように、人は無意識のうちに自分の行動様式の中に「こうしたらこうする」という道筋をつくり、それを繰り返すことで固定化していきます。
遅刻を頻繁にする人も、実はこの“道筋”を自分の中に作っています。 例えば、「就寝前にいつも別のことを思い出し、それを済ませないと眠れない」「朝起きたら必ず天気予報を確認しないと落ち着かない」「出発の時刻ぎりぎりまで別のことを続け、結果としていつも1〜2分遅れてしまう」など。こうした行動が、本人にとっては「夜の就寝前から朝の出発前に必ず通る道筋」になってしまっているのです。つまり、遅刻は“怠惰”や“だらしなさ”ではなく、その人が無意識のうちに自分の行動様式の中につくってしまった道筋の結果、すなわち心の構造の問題なのです。そして改善するためには、まず本人がそのことを自覚したうえで、一度つくってしまった道筋を壊して、“ゼロ”にする必要があります。
努力している自分を客観視する
世の中には努力している人が大勢います。一生懸命に勉強している人もたくさんいます。しかし、ただがむしゃらに努力するだけでは、より善い人生を歩むことはできません。では、どうすればよいのでしょうか。答えは簡単です。ときどき自分を客観視することです。今いる場所から少し離れて、「自分は今どこにいるのか」「この行動の先に何があるのか」「自分はどこへ向かいたいのか」――そう問いかけてみるのです。そうすれば、不足している点や改善すべき方向性が見えてきます。
人生はあっという間です。一人の人間が一生のうちに使える時間とエネルギーには限りがあります。だからこそ、目の前のことだけにとらわれるのではなく、自分が今どこにいて、どこを目指すのかを見据えたうえで歩んでいく必要があるのではないでしょうか。
決めたことを続けることが一番難しい
「健康のために毎日運動しよう」「上手になるために毎日練習しよう」「毎日少しずつ勉強しよう」・・・。このように、自分で何かを決意して始めた経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。人は皆、「自分を改善・向上したい」「より善く生きたい」と願い、そのための方法を考え、実行を決意します。そして最初のうちは、決めたとおりに行動します。ところが時間が経つにつれ、ほとんどの人がそれを途中でやめてしまいます。しかし、この“自分で決めたことを毎日続けられるかどうか”が、その後の人生を大きく左右します。
偉大な発明家トーマス・エジソンの言葉に、”Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.”(天才は1%のひらめきと99%の努力である)という言葉があります。ひらめきは誰にでもあるものではありませんが、努力は自分次第です。つまり、自己実現できるかどうか、自分の望む人生を歩めるかどうかは才能の有無ではなく「決めたことを続けられるかどうか」ということにかかっています。ビジネスの世界でもスポーツの世界でも、何かを成し遂げている人は、継続的な努力を積み重ねている人です。反対に、どれほど立派なことを言っても、それを行動に移せない人、続けられない人は、何も達成することはできません。
人生を変えるのは、能力や才能ではない。一事が万事において、継続的な努力そのものである。 (『生井利幸哲学格言全集 Ⅰ 牢獄からの脱出』(生井利幸著/TN英知研究所/2025年)109頁より)
一生の間に認識・経験する範囲は、通勤経路ほどの狭さでしかない
人間は、生まれてからこの世を去るまでに、数えきれないほどの経験を積み重ねます。幼少期は、両親や親戚、近隣の人々との関わりから始まり、学校に入ると、学校生活を通じて交友関係や社会的なつながりが広がっていきます。やがて社会人となり、さらに多くの人と出会い、仕事や生活を通じて経験の幅が広がります。そして晩年、自らの人生を振り返ったとき、実に多くの出来事があったように思えるでしょう。
しかし、実際には、一人の人間がこの地球上で認識・経験できる範囲は、人類が歩んできた歴史や広大な宇宙空間に比べれば、家から会社までの通勤経路ほどの狭さでしかないのです。つまり、人間は極めて限られた範囲の中で物事を考え、判断しているということです。このため、自分の理解や判断が「正しい」と思っていても、それはしばしば勘違いや思い込みに基づいているのが現実なのです。
私たち人間は、毎日さまざまなことに直面し、その都度、感じ、考え、判断しながら生きています。その際、前述のことを念頭に置いて、「自分は間違っているかもしれない」と少し立ち止まり、より視野を広げて落ち着いて考えるなら、よりよい方向へとつながるのではないでしょうか。
人間の気づきというものは、猫の目ほどの狭い気づきでしかない。 (生井利幸公式サイト「今日の言葉」より)
時間とは、あってないようなもの
「時間とは、あってないようなもの」とは、いったいどう意味なのでしょうか。
「今」は確かに存在します。今この瞬間、息をして感じて考えている自分自身がここにいます。
では「過去」はどうでしょうか。分かりやすく言えば「昨日」、ほんの少し前のことです。記憶として残っているため、あるよう思えます。しかし、実体としては存在しません。理論上「過去に戻る」という話はできるかもしれませんが、実際に戻ることはできません。
次に「未来」。例えば「1時間後」「明日」はやってくるように思えます。1か月後、3か月後、1年後、3年後・・・、自分は生きているだろうと考えます。未来はあるように思えます。しかし、それは人間の勝手な思い込み、妄想にすぎません。1時間後に大地震が起きないとは限りません。家を出た瞬間に隕石が落ちてくるかもしれません。今は健康でも、1か月後に治らない病気が見つかるかもしれません。明日が来る保障は、どこにもないのです。
緊急事態は日常的に起こり得るもの。人間はその狭間で生きています。生きていられることは決して当たり前のことではなく、むしろ幸運なことなのです。だからこそ、今ここに自分が存在していることに感謝し、今のこの瞬間を大切に精一杯生きる必要があるのだと思います。
明日ではない。本日のこの瞬間において生きていられること自体が奇跡である。 (生井利幸公式サイト、「今日の言葉」より)
人は「嘘」が好き
「一日にたった5分これを聴くだけで英語がペラペラになる」「半年で劇的に英語力が身につく方法」「寝ている間にお金が増える」「1万円を1億円にする方法」――こうした文句は街の至るところに溢れています。人は「楽をして得する方法がある」と聞くと、つい心を奪われてしまいます。冷静に考えれば、そのような方法は存在しない、即ち「嘘」だと理解できるはずなのに、信じてしまうのです。
言い換えれば、人は「都合のよいこと」「心地よいこと」「望んでいること」を言うと寄ってきて、逆に「都合の悪いこと」「耳の痛いこと」を言うと離れていきます。つまり、人は嘘を好み、本当のことを言われるのを嫌がるのです。しかし、あなたにとって都合のよいことばかりを並べる人と、たとえ厳しくても本当のことを言ってくれる人――どちらがあなたの真の幸福や成長を願っているでしょうか。
親は子どもに対して、嫌がられても「悪いことは悪い」とはっきり言います。時には厳しく叱ることもあります。しかしそれは、子を心から愛し、幸せを願っているからです。このことは、他者との関係にも同じように当てはまります。
もしあなたの周りに、厳しいことであっても本当のことを言ってくれる人がいるなら、その人を大切にすべきです。その人こそが、あなたのこと真剣に考えてくれている人だからです。多くの人は「良くない」と思っても見て見ぬふりをし、心の中で笑ってやり過ごします。なぜなら、口にすれば関係が面倒になることが多いからです。一方、都合のよいことばかり言う人は、あなたのためではなく、自らの利益のためにそうしているにすぎません。そのような人の周りには、一時的に人が集っても、やがて離れていきます。
人に対して本当のことを言うのは、決して容易ではありません。それでも、心の中で笑ってやり過ごす人間であるよりも、相手の真の幸福のために真実を伝えられる人間でありたいものです。そして、本当のことを言っても離れずにいてくれる人がいるなら、その人とは、仕事においても私生活においても、かけがえのない本物の関係を築くことができます。
自分にとって耳が痛いことを言う人ほど、本当に自分を心配し、気遣っている人である。
耳が痛いことを言わない人は、自分の行く末を心配していない人である。
(生井利幸公式サイト、「今日の言葉」より)
「分不相応のお金を手にすると、後に大変な思いをする」
「お金はあればあるほどよい」「できるだけ多くのお金を労せずして得たい」と考える人は少なくないでしょう。 しかし、分不相応のお金を手にすると、後に大変な思いをすることになります。以下に具体的な事例を挙げます。
(事例1) 飲食店の契約社員として働いていたAさんは、あるとき正社員に登用され、それまで月給22万円だったのが急に36万円になりました。Aさんは、自分がお金持ちになったような気分になり、見境なく浪費してしまいました。
(事例2) 芸能界で子役スターとして活躍していたBさんは、子役時代には超売れっ子で、自宅から撮影現場まで運転手付きの車で送迎されていました。ところが大人になると仕事が激減し、やむなく一般の仕事に就くことになりました。しかし現実は厳しく、子役時代との落差は天と地ほど。相当な苦労を経て、今では自分が運転手をしているそうです。
(事例3) 両親が大金持ちだったCさんは、普通の人が必死に働いても得られないほどの大金を、毎月のお小遣いとして受け取っていました。その結果、Cさんの周りには金目当ての人々が集まり、最後には犯罪に手を染めてしまいました。
お金は本来、多くの苦労を重ね、自分が流した汗の対価として受け取るものです。若い時に労せずして大金を手にすると、金銭感覚が麻痺し、結果的に大変な思いをすることになります。「分不相応のお金を手にすると、後に大変な思いをする」、言い方を変えると、「収入は自分の品位・品格に見合ったものであること、分相応であることが望ましい」という意味なのです。
最後に、若い人へのメッセージを贈ります。「若い時に苦労してやりくりした経験は、自らを成長させる肥やしになる」
「なりたい人」になるには、「なりたくない人」を見る
人は誰しも、「もっと自分を改善・向上したい」「理想とする人に近づきたい」という願望を持っています。そしてその願望を叶えようとするとき、多くの人は理想とする人物を見て、その人のようになろうと努力します。しかし、理想の人というのは、そこに至るまでに、他人からは見えない相当な努力を積み重ねてきた結果の表れです。そのため、結果だけをどのように観察しても、理想に近づくための具体的なヒントは得られません。仮にヒントが得られたとしても、簡単に真似できるものではありません。
では、どうすればよいのでしょうか。答えは簡単です。理想の人に近づくには、理想の人を見るのではなく、理想とは反対の人、「あのようにはなりたくないと思う人」をよく観察するといいのです。そうすると、そうならないためのヒントが満載であることに気づきます。つまり、「なりたくない人がしていることを、しないようにする」――これこそが、理想に近づくための現実的な方法です。
例えば、痩せたいと思うとき、スレンダーな人を見て憧れるよりも、太っている人の生活習慣をよく観察し、その人がしている習慣をやらないようにする方が効果的です。また、品のある人になりたいと願うとき、上品な人を真似しようとするより、「あのようにはなりたくない」と感じる人の言動を反面教師にする方が、自身の振る舞いを確実に改善することができます。
「なりたくない人を見る」、これは決して誰かを批判・否定するためではなく、他者の姿を通して自分自身を見つめなおし、自身の改善・向上のための気づきを得るための方法なのです。
今日からぜひ、スーパーで買い物をするとき、電車に乗るとき、街を歩くときなど、日常の中で「理想の人」を探すのではなく、「なりたくない人」を探して、よく観察してみてください。きっと、さまざまな気づきが得られるはずです。
所有欲を捨てると幸せになれる
“死ぬときは何も持っていけない”と知りながら、死を迎えるその日まで所有欲に支配されるのが人の常。 (生井利幸公式サイト、「今日の言葉」より)
私たちが人間らしく暮らすためには、住む家が必要であり、場所や仕事によっては車も欠かせません。しかし、多くの人は必要最小限のものだけでは満足できません。むしろ、物を持てば持つほど、さらに欲しくなるのが人間の性です。では、物をたくさん所有することは本当に幸せなのでしょうか。
アメリカの大学で教鞭を執るある教授は、書斎を整えることもなく、いつも地味なスーツを着て、大学の研究室や図書館で仕事をしています。多くの教授は、図書館では学生に話しかけられるため、自宅の書斎で一人で仕事をするものです。しかし、その教授は違いました。ある時、別の教授が「私は自分の書斎で仕事をした方が落ち着きます」と言うと、彼は次のように答えました。「私が仕事をしている場所が、私の書斎なのです。図書館が私の書斎です。」
もちろん、社会の中で生きていくために必要なものはあります。何も所有してはいけないということではありません。しかし、彼のような考え方をほんの少し取り入れることができれば、必要以上に物にとらわれることはなく心豊かに生きることができるのではないでしょうか。
不要なものを持たない人こそが、最も豊かに生きれる人である。(生井利幸公式サイト、「今日の言葉」より)
世の中は謝罪で成り立っている
「謝罪に来たのか、言い訳に来たのかわからない」「誠意がまったく感じられない」。そんな経験をした人は少なくないでしょう。これは、謝罪する側が相手ではなく自分を守ろうとする一種の自己防衛本能によるもので、当人には気づきにくいものです。しかし、謝罪の仕方を誤れば、望まない結果を招きます。ご近所付き合いなら関係が悪化し、ビジネスの場では取引の継続に影響し、最悪の場合は会社の存続すら揺らぎます。そのため、謝罪の重要性を痛感している企業の社長や役員からは、「営業管理職向けの研修に謝罪の方法を含めてほしい」という依頼が多く寄せられます。では、どのように謝罪すればよいのでしょうか。
第一に、「謝罪するときは、謝罪に徹すること」です。言い訳や自己保身が一言でも混じれば、それはもはや謝罪ではなく、相手に不快感を与え、信頼をさらに損ないます。謝罪とは、相手に自分を理解してもらうための行為ではなく、関係を修復するための重要なプロセスです。ある意味、マイナスからのスタートであり、新たに信頼を得るよりも難しいのです。
第二に、必要な場面では、できるだけ早く謝罪することです。もちろん、早く謝罪したからといってすぐに関係が修復するとは限りません。しかし、謝罪することで、それ以上状況が悪化することはありません。逆に、時間が経てば経つほど、相手の不信感は増していきます。また、実際の謝罪の場面では、相手としっかり向き合い、誠心誠意謝る姿勢が必要不可欠です。
実際、謝罪は企業の社会的信用に直結します。 ある複製画の制作会社では、納品後に作品の細部の誤りを指摘されました。複製画は特別なもので、その指摘は、深い教養と作品に対する相当な思い入れがなければ気づかないようなものでした。そのため、社長自らがクライアントのもとへ出向き、親子ほど年の離れた相手に対して深々と頭を下げ、最終的に作品を作り直しました。簡単にできることではありません。しかしその姿勢が信頼を回復させたのです。もしここで誠実な対応をしていなければ、信頼をなくしていたでしょう。また、この例は、謝罪とは単に「謝ればよい」というものではなく、相手を知り、相手に応じた対応が求められるということも示しています。
こうした姿勢は企業だけでなく、私たちの日常生活においても同じです。 例えば、都心のマンションでは生活音をめぐってご近所からクレームを受けることがあります。クレームを受けたときは、まず謝罪します。そして、時間を置かずに改めて誠意を伝え、相手の気持ちに寄り添う姿勢を示します。音の感じ方や事情は人それぞれであり、ここで大切なのは「自分の事情」ではなく「相手がどう感じたか」です。一度購入した家は簡単に買い替えられません。だからこそ、快適に暮らしていくためにも、適切な謝罪を通じて関係を維持することが欠かせないのです。
謝罪とは、単なる儀礼的な行為ではなく、適切な関係を維持し続けるための大切なコミュニケーションです。相手の痛みや怒りに寄り添い、誠意をもって向き合うことこそが、真の謝罪に繋がります。そうした誠意ある姿勢を積み重ねることで、私たちは相手との関係をより健全に保つことができます。誠実に謝罪できる人や組織は、結局のところ、長く信頼され続けます。